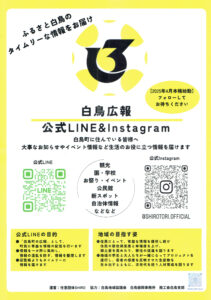「クリーンなジビエ事業」を進めるために
3月の一般質問が終わりました
今回は大項目が「狩猟文化と森林資源について」、小項目で「ジビエ業」「猟友会」「郡上グリーンプロジェクト」の3点を取り上げました
これからブログで補足・解説をしていきたいと思います
まずは「ジビエ業」です
00.00~2:38 導入部、リンゴの木の話
2:38~14:49 ジビエ業と廃棄物について
とって言っても、ジビエ業を手放しで称賛するようなものではなく、その「負の側面」を取り上げています
SDGsとか、利活用とか、森の恵みとか、命をいただくと言いながら、公金を数千万使って、大量の不法投棄を行っていたら、どうでしょうか? 地球を救う?美しい森をジビエで救う?
とてもおかしいですね これでは詐欺です
俗に言う公金チューチューNPOと構造的にはなんら変わりありません
決してジビエに反対しているわけではなくて、むしろどうしたら、「クリーンなジビエ事業」を推進していけるか、その問題意識を共有して欲しくて取り上げました
まずはご覧ください

さて、これは捕獲後の鹿や猪が不法投棄されている様子ですが、プール状の堀を作って、そこにどんどん鹿や猪を投げ込んでいくというスタイルです
ジビエ業と共にしばしば地域で問題になりました
どれも形状など類似性があります
だいたい、一辺5~10mくらい 大きいものだと小学校の教室ぐらいの広さになります
規模によりますが、年間で200~300頭余りから生じる残渣が捨てられることもあります
あまりにも堂々としていますから、一見、公式の処分場?に見えるんですが、これはもちろん違法です
本来、捕獲後の野生鳥獣の処理は厳しく法律で定められています

どうして、こういうものが山中に出来るかというと
まず第一に「鹿が大量に増えたこと」、第二に「大量に捕獲した鹿を処分しなければならなくなったこと」、第三に「鹿の利活用」といった触れ込みで「無計画にジビエ施設が増えた」といった背景があると言われています
これは鹿に限らずですが、基本的に野生動物というのは「歩留まり」が悪く、ジビエで利活用出来るお肉は、三分の一、四分の一だと言われています(説明すると長くなるので割愛しますが、これでも多い方だと思います)
実は、大部分は廃棄しているのが実態なのです
(※ちなみに家畜は産業が確立しているため、様々な部位が過製化され、最終的に廃棄されるのはわずか5%前後だと言われています ジビエとは比較にならないほど利用率が高いのです 世の中に誤解されていますが、利活用で最もサステナブルなことをしているのは、ジビエではなく、むしろ畜産です)
それで、ジビエ施設というのは、規模が大きくなればなるほど、鹿を集めれば集めるほど、大量の廃棄物を作り出してしまいます
また、原料を猟師さんたちが調達してくれるとは言え、僅かな可食部のために大変なコストを割かねばならず、事業としては効率が悪く、利益が出にくい構造をしています
そうすると、大量の残渣の処分に困り、不法投棄が始まります
あるいは田舎だとコンプライアンスへの意識が低く(というか全く欠如しており)、最初から山に捨てる前提でジビエ施設が始まってしまうこともあります
もともとジビエ事業は国策であり、法整備が始まったのも2014年付近からで、比較的新しい事業です
地域振興と獣害対策をかけ合わせ、鳴り物入りで始まったのですが、当初から見通しの甘さが関係筋からはよく指摘されていました
というのも、捕獲後の残渣・処理の問題は「ジビエ業だけ」では解決しませんし、ジビエ業自体は一種の食肉加工業であり、これで鹿や猪など獣害自体が「減るわけではない」からです(要は単なるお肉屋さんですからね)
さて、プール状の不法処分場ですが、これが出来てしまうと、どんな問題があるでしょう
まず第一に生態系への影響と人、家畜への安全性の問題です 加えて地域振興、ジビエ業、自治体への信頼の失墜 また狩猟者、ジビエ関係者のモラルの低下 どれも深刻な問題です
大量の動物の死骸が廃棄されると、土壌に過剰な硝酸態窒素が生成されます
硝酸態窒素は植物に必要なんですが、過剰にあると逆に生き物に毒性を発揮します
水道水、地下水、あるいは野菜に含まれる硝酸態窒素は高濃度になると明らかに人体に危険であり、近年ではPFASと並んで昨今問題となっています
WHOやEUでは今や水質基準に硝酸態窒素の項目を設けてますし、環境省でも令和3年に既にガイドラインが出来ています

次に防疫上の問題ですが、野生動物は、家畜のように衛生上管理された環境にいません
様々な病原菌、ウィルス、寄生虫の塊です
それらが死骸を求めてやってきた昆虫、鳥類、小動物によってまた拡散するわけです
一説によるとこうした不法投棄が鳥インフルエンザや、豚熱、口蹄疫などの家畜伝染病の一因ではないかと言われているほどです
家畜伝染病はワンシーズンで数百億~数千億の被害を出しますから、これは社会に対して本当に驚異的だと言えます
一種のバイオハザードだとか、バイオテロですね
そして最後に、これも本当に問題なのですが、狩猟者や関係者のモラルが徹底して低下していくことです
あそこであんなことしてるんやったら、オレらもやってもええよね?うちのとこにも穴作ろうぜ?となるわけです
だんだんモラルが低下していき、鹿や猪を獲ったら、そのまま、そこら中に放置するようになります
山の中、あちこちに死体だらけ、動物の糞だらけ、それ+鹿の食害だらけになります
どうでしょうか、こんなことをしておきながら、ジビエで地球を救うとか、美しい森をジビエで救うとか、いかにも薄っぺらい嘘です
ジビエ業でひとたび不法投棄が始まり、それが常態化すると、様々な方面へ実に様々な悪影響を及ぼします
「こうなるとほぼその地域でジビエ業は出来なくなる」とあるアドバイザーは言っています
狩猟文化も壊滅的にダメになってしまいます
もし、過激な環境団体がこれを見つけてSNSなどにアップしたら大炎上するでしょう
警察や保健所の立ち入り調査が入れば、関係者は刑事責任を問われるでしょう
世間の明るみに晒されたら、ジビエ業のイメージは悪くなるし、市の信用も落ちるわけです
これをしている人、関係者の人達は、おそらく罪の意識など希薄でしょうが、実に多大なリスクを人や社会に、そして自然に押し付けているのです
ジビエ事業を推進するなら、まずこういった問題をクリアしていく必要があります(そんな簡単なことではないのですね)
まず、捕獲した個体の処理方法をどうするか
廃棄物の処理とジビエは事業としてはもう「セット」で考える時代です
本当言うと、ジビエ施設より、専用の処理施設や、回収手段などを先に確立することの方が大事なくらいです
また、コンプライアンスを意識しながら、計画的に事業を進めていくこと、地域の猟師さんたちと優良な関係を築くことも必要です
そのためには関係者のコミュニティから見て、今自分のしている事業がどう見えているか?といったことにも気を配れないといけません
無茶な要求や、相手を傷つけるような言動、不法投棄などなど、文化、社会に不利益をもたらす行為が続けば、コミュニティから孤立してしまうでしょう
それではジビエ業は成功しません
昭和のワンマン経営者のような取り組み方ではジビエ業は成功しないばかりか、地域社会に不利益しかもたらさない、周囲の誰もハッピーにならない、それはもはや「公害」です
今後、ジビエ業やりたい人が高鷲や美並からきっと出てくると思います
その時に、彼らが真面目に、気持ちよく取り組めるように「クリーンなジビエ業」を目指して欲しいと思います
悪い習慣は、あとからやって来る人たちのためにも絶対に断ち切らないといけません