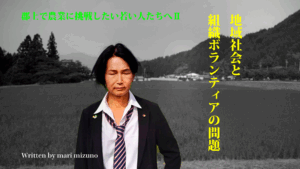参院選振り返って

党派性より勝った個性と人柄
永かった参院選の闘いが終わった
大局で自公は大敗に終わったが、岐阜では野田聖子氏に次ぐ新しい女性国会議員が誕生した
自公にとって本当に厳しい闘いだったが、からくも岐阜は死守された
しかし、若井氏だったからこそ、この逆境で勝てたのだろうとつくづく思う
これが、もし「男性」で、いかにも「自民」らしい「先生」タイプの、つまり「ステレオタイプな男性政治家」のイメージに収まってしまうような人を立てていたら、おそらく岐阜の自民は立ち直れないレベルの負け方をしていたのではないか…
そこには「女性」であるという属性に加えて、若井氏のキャラクターや経歴が大きく働いたはずだ
どこか演歌歌手のような華やかさと親しみのある庶民性、その一方で全国制覇、世界制覇を空手道で成し遂げたという荒々しさと力強さ
半身不随から復活したアスリートから、野田聖子氏に見出されて政治家に転身するという人生
「笑顔は希望、やさしさは力」というスローガンは柔剛併せ持つ彼女にぴったりのキャッチコピーだ
10年県議会に尽くしてきたという実績もある
そこからにじみ出てくる個性と魅力が、自民への不満を上手く受け流していったように思う
言ってみれば、今の自民らしくない、なにか「新しさ」が彼女には確かにあった
それが強烈に人々を惹きつけた結果だったのだろう
「自民党」というより「彼女が選ばれた」、そう言ってもいいのかなと個人的には思っている
伸び悩んだ立憲
それに加えて、立憲が伸び悩んだというのも勝因のひとつだろう
これは全国的に見ても言える
岐阜のように一人区でもあと一歩で競り負けしたという福島、岡山
茨木では自参に負けて3番手
福岡では自参公と4番手の国民に負けて、立憲はまさかの5番手なのである
立憲が予想以上に弱かった…というのはやや意外ではなかっただろうか
というのも、選挙前まで世論は、自民は立憲に負けるというムードだった
ところが開けてみると思ったほど振るわなかった
立憲が弱かったから自民は少し助かった
ところで、郡上市だが、前回の衆院に引き続き、ここでも負けたら一体どうなるか内心ハラハラしていた
郡上市のような地方の自治体にとって、中央に声が届く国会議員が地元にいない、身近に頼れる国会議員がいないことは現実的に死活問題である
もちろん現在の自民のあり方、政策の様々な点において「問題がない」とはとても言えない
だとしても、だからこそなのだが、中央に自分たちの声を届け、実質的な実行力を発揮できる与党代表を地元から送り出し続ける…ということが必要になる
例えば、今年始めの豪雪被害で郡上市は瞬間的に10億円、シーズンを通して20億円近い支出があり、財政調整基金が底をつくという緊急事態に陥ったが、まもなく国から特別交付税がおりた
これも、郡上市のために動いてくれる与党の国会議員がいるからなのである
これは地方にとって生存戦略の問題であり、イデオロギーの問題ではない
まあ、強いて言うなら日本の制度の問題だろうか
しかし、それはすぐどうこうできるものではない 地方の自治体としては生き残るためにどうするべきなのか今できることを考えるしかない
その立場は戦国時代の小国のようなものである
振興政党デビュー戦
今回は選挙期間中、若井陣営の選挙事務所に通っていたが、党本部への違和感や批判が応援演説のスピーチでしばしば聞かれたのが印象的だった
「自民は嫌いになってもいいけど、若井は嫌いにならないで」といった自虐ギャグもあった
党を代表する議員として応援に駆けつけながらも、口々に似たことを言わねばならなかった議員らの胸中を察するとやるせない
後半戦の現場には「もしかしたら負けるかもしれない」といった緊張感も漂っていた
こうした中で若井あつこ氏は勝ったが、自民党は負けた
二度大敗し、事実上の少数与党(比較第一党)となってしまった
案の定だが石破首相は続投を表明し、今の自民と組むのは得策ではない、次の選挙で負けかねないのだから野党はどこも組ないと表明している
政局なんていつも過渡期と言えばそうなのだが、今回こそは色んな意味で自民党の存在意義が問われたと思う
また、伝統政党と呼ばれる自民、公民、立憲、共産、社民などが衰退する一方で、国民、参政が振興政党として躍進した 「振興政党」デビュー戦のような選挙だった
振興政党の発展によっては、もしかしたら後に「歴史的」と言われる選挙になるかもしれない