郡上で農業に挑戦したい若い人たちへⅡ
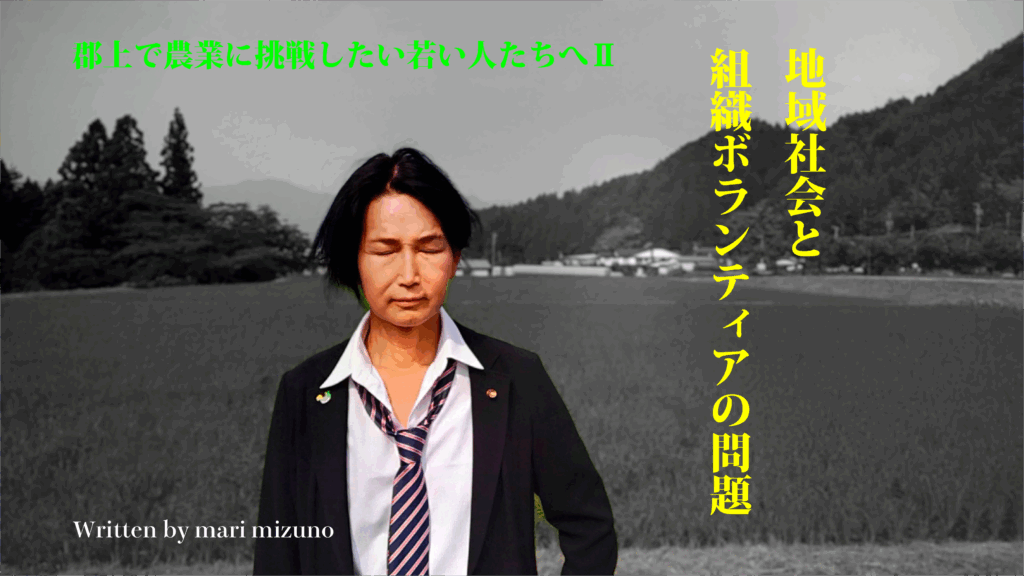
地域社会と組織ボランティア(支援団体)の問題
ここでは一般の人を動員する「ボランティア組織」「NPO団体」といった支援団体の活動とそのあり方の問題点について述べます
付随して、そうした団体に我々議員や行政はどう関わるべきか、地域の人たちはどう接していけばいいかという問題も扱います
前章で述べたように支援団体が必ずしも被災者(例えば農家さん)を代弁しているか、あるいは地域住民から承認されているかというと、実はそうではないという場合がしばしばあります
(※ここではあくまで一般論として問題化しています 「農家さん」や「団体」は特定の個人や団体のことではありません)
寄付の「使途」と団体の実態
例えば、団体が『被災者へ分配される義援金(寄付)ではなく、被災者を支援する活動への寄付だ』とうたって寄付を募っている場合、それで集まったお金は被災者(例えば農家さん)には入りません
これは被災者を直接支援する寄付ではなく、支援活動を行う団体への寄付なのです
予めそう明言しているので違法ではありません
紛らわしい表現で集金した場合は詐欺罪に問われる可能性が高くなります
しかし、一般人には団体の言う「寄付」が一体何を意味しているのか、よく判らないでしょう
単純に「被災者を支援するための寄付」だと思っている人もいるかもしれません
このお金は団体に帰属し、支出の判断は主宰者に委ねられ、使い道が外部からは見えにくい構造になっています
もちろん、支援活動にも光熱費や人件費、雑費など経費は必要ですが、逆に言えば経費を作るために支援活動を行うことも可能です
慈善団体やNPOにとって資金集めは手段であって、主眼は社会貢献活動であるはずです
しかし、それが転倒し「資金集め」という手段が自己目的化している団体や主宰者も存在します
そうした団体、主宰者にとって「支援活動」は、人々の「共感」や「同情」に依存した「集金スキーム」です
こうした団体は各地で災害が起こる度に出かけてゆき、活動費として「寄付」を集め、国や行政に補助金の申請を行います
これらは合法の範囲内で行われており、支援活動にも有益性があるので、被災地における「偽装ボランティア」など明確な詐欺とは異なります
しかし、立場の弱い被災者や災害という悲劇を利用して資金を得る構造は、俗に言う「弱者ビジネス」と本質的に同じです
支援の名を借りた関係の非対称性
厄介なことは、こうした団体の支援活動には被災者(例えば農家さん)自身も関与していることがほとんどだということです
団体の活動に被災者が参画していると、外側から見て、まるで団体が当事者団体のように見えてしまいます
被災者は窮地に立たされているので団体の支援を断れませんが、そのことによって団体の正当性が担保されるのです
仮に支援活動が有益なものだとしても、団体の活動を被災者(例えば農家さん)の人たちは心の底でどう感じているかということが本当に大事なことではないでしょうか
もしかしたら言葉には尽くしがたい、非常に複雑な気持ちではないでしょうか
あるいは、地域の農村、集落がこうした団体の活動の場となってしまっていることを、その地域の人々は正直なところ、一体どう感じているでしょうか
ここには「支援する側/支援される側」の関係が実は非対称で理不尽なものだということに留意する必要があります
政治や行政、メディアが与える「お墨付き」
ところで、団体が地域社会に認められているかどうかは、マスコミや我々政治家、行政の人からは見分けが付かないものです
ましてや被災者自身も関わっていると本当に分かり難いものです
活動がメディアに取り上げられ、SNSでも拡散されることで、団体がまるで「被災者の代表」のような立場になってしまうことがあります
そこで議員や行政が団体と接触し、視察や補助金の話を始めたら、すっかり団体が集落の公式窓口のようになってしまうでしょう
こうして災害で集まって来る人たちが団体に「お墨付き」を与えていきます
団体に政治家や行政、企業が付いてしまうと、その団体の発言力や政治力はもはや強大なものとなり、地域住民ですら意見することは困難になるでしょう
そうやって団体は地域に根付き、成長していきます
①表向きは「被災者支援」、実態は「団体の活動費」
「被災者のため」とされる一方、資金はNPO職員の人件費、交通費、事務所経費などに充てられている
会計が不透明
法律上「寄附金の使途」についての明確なルールはない
「善意の寄附」と「実質的な営業活動」の区別は曖昧
②「自分たちが活動しているから被災者は助かっている」という構造
寄附を原資に支援活動すること自体は一見有益
しかし、支援の主眼が「自己目的化」や「組織の維持」に向いてしまうと、本来の目的である被災者の自立支援や行政連携は集金のための「方便」に過ぎなくなる
③「共感消費」「自己満足の倫理」に依存した「集金スキーム」
メディアで活動をアピールすることで共感を呼び、寄附を集める
可視化された活動はごく一部であり、被害者、当事者とは乖離がある
寄附者も「寄附したこと」に満足してしまう
④政治家や行政、企業が団体に付くことで正当性が担保されていく構造
当事者団体、地域の任意団体に見える 見分けが付きにくい
政治家はプロパガンダに利用したいという欲望が強く働く
結果的に団体の力を補完してしまう問題
さて、こうした団体、主宰者と地域の人々や農家さんは果たしてどう付き合っていけばいいでしょうか
主体的な関係性
このような現状を前に言えることは、地域の側が“受け身”にならず、主体的に関係性を築いていく必要があるということです
具体的には前章で述べたような、当事者による「共同体」がしっかり形成されていることが重要なポイントになります
農家さん同士の共同体があれば、これがそのまま被災者の当事者団体となるわけです
日頃から行政やJAとリレーションをとっておけば、災害時の情報共有や支援要請もスムースに行えます
支援や寄付も、自分たちで情報を発信し(声を上げて)、人を動員し、資金を集めることも出来るのです
自分たちでやれば会計上も明瞭です
①当事者による当事者団体を作る
②当事者として情報発信する 声をしっかりあげる
③支援団体の受け入れ、対応も団体同士で行い距離を取る
つまり、そもそも自前の共同体があれば、目的や素性が判らない任意団体の力を借りなくても済むのです
また慈善団体やNPOが入植しても団体で対応することが出来ます
既に定着してしまった団体、主宰者との関係作りも互いに団体単位で距離を取りながら行うのが理想です
「当事者」として思っていることをはっきりと伝え、必要な時は毅然とした態度を取りましょう
一見して有益な支援であっても、地域社会の為になるかどうかよく考え、場合によってははっきり断りましょう
このように自分たちが集団であれば不本意な関係性も回避出来るのです
農家さんたちがそれぞれ孤立していては出来ません
集団でいるからこそ持てる交渉力なのです
議会、議員に求められるもの
議員には「地域の人に認められたい」「自分を知って欲しい」という承認欲求があります
これ自体は悪いことではないのですが、災害時には裏目に出ることがあります
手段と目的が転倒した慈善団体ではないですが、議員もこれがチャンスとばかりにスタンドプレーしてしまうのです
①スタンドプレーの回避と情報共有の徹底
②視察やヒアリングの際は公式な地域組織を通すこと
③任意団体との接触・広報には慎重な配慮を
「被災地で議員がスタンドプレーしない」というのは、災害支援や、災害時におけるBCP(Business Continuity Plan 事業継続計画)おいても鉄板です
かえって現場が混乱し、行政や関係部局が消耗してしまうからです
このような場合は議員同士が情報を共有しながら行動は慎重に行うことになります
現地への視察、ヒアリングなども委員会単位で、公式の地域組織を通して行うのが推奨されます
これは目的や素性が判らない任意団体に議会や議員がうっかりコミットしてしまうことを避ける意味において大事なことです
行政に求められること
行政としては慈善団体やNPOに補助金を出す際の制度の厳格化といったところでしょうか
災害支援に関わるNPOには、認定制度、補助金支払後の会計の透明化、第三者機関によるモニタリングを義務付け、不正を防ぐことが必要です。
①補助金制度の会計透明性要件の導入
②NPO等に対する事後監査・報告義務の整備
③「資金集め目的」の団体を排除する環境の整備
地域の人々が安心して暮らすためには、資金集めが目的の慈善団体が居心地の悪い自治体を目指すべきかと考えます
市民に求められること
さて、市民の皆さんにとって、寄付先の見極めは簡単ではありません
一度冷静になって、ボランティアの作業内容、その目的や有用性について考えてみてはどうでしょうか
例えば、クラウドファンディングでも立ち上げて、集まったお金をそのまま当事者(例えば農家さん)にお渡しすることも出来るわけです
制度的支援が届くのには数ヶ月~半年間の時間が必要なので、一時的な支援より、その間を食いつなぐ資金援助の方がむしろ有効かもしれません
これなら補助金の対象から外れてしまった農家さんにも、直接的な支援を届けることが可能になるかもしれません
また昨今では補助金とクラファンの間にある「地域型財団・地域内ファンド」といった制度もあります
①寄付先の見極め
支援活動の目的、有用性、会計の透明性、団体の下調べなど
②他の利用出来るサービス
クラファンやフィロソフィー事業を行う企業のサービスなど
安全性、自分にかかるコストやリスクも計算に入れる
③公的な補助制度を知ること
一定の知識は必要
ちなみに自然災害等による制度的支援というのは、被災者が何らかの形で申請手続きをすることで可能となります
ですから支援団体がSNSなどで声を上げても、上げなくても、活動をしてもしなくても、そもそも論として補助金は被災者が手続きさえ怠らなければちゃんと付く(※)のです
(※対象基準はあります 非対象者になることもあります)
さいごに
共同体の意味
かつて「共同体の喪失」が問題とされた時代が何十年も前にありました
社会学・都市論においてcommunity lost(コミュニティの喪失)がキーワードになったのは、70年代の後半から80年代にかけてです
農村部からの大規模な人口流出が完了し、さらに都市部では「核家族化(※)」「人間関係の希薄化」「町内会・自治会の機能低下」などが可視化され始めます
それから何十年も経ち、かつてあった青年会、婦人会は消えていきました
現在は自治会と同様、かつては地域力の象徴であった消防団もその維持と機能が危ぶまれるようになりました
(※日本の核家族は戦前からあったがその時点では問題化されなかった 都市部に集中し、それが共同体の喪失と共に社会課題として認識されるようになった)
しかし共同体が失われていったのは社会構造の変化によるもので、私たちにとって共同体を持つことの意味が失われたわけではありません
郡上のように中山間地域で農村や集落が数多くを存在する地域において、共同体の持つ意味はより重いものになりつつあります
農家さん同士の共同体、各種協議会や保存会、市民グループなど、今一度、身近にある地域組織を見直してみましょう

